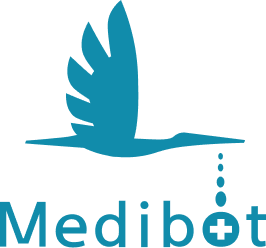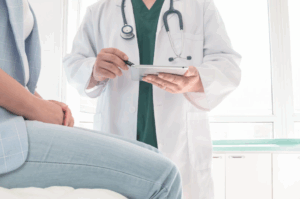自費診療クリニック向け|オンライン診療の始め方ガイド|準備から運用までの7ステップ

ここ数年、美容医療やAGA、ED治療、矯正歯科など、自費オンライン診療の波が押し寄せています。
コロナ禍をきっかけに非対面診療が一般化し、患者の利便性を高めながら収益性を向上できる手段として、導入を検討するクリニックが急増しました。
とはいえ、初めて導入する院長や経営者の中には、下記のようなお悩みを抱えている方も多いはずです。
- 「興味はあるけれど、何から始めればいいのかわからない」
- 「ツールやシステムの選び方を間違えたくない」
- 「患者さんに本当に受け入れられるのか不安」
本記事では、自費オンライン診療をスムーズかつ効果的にスタートさせるための7ステップを、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、導入の全体像と具体的な準備内容、失敗を防ぐためのポイントが明確になり、「明日から動き出せる」状態になれます。
1. 自費診療クリニックにオンライン診療が必要とされる背景

患者ニーズの変化
自費診療は保険診療と比べて単価が高く、リピート率が収益の安定性を左右します。
オンライン診療を導入することで、患者は通院にかかる時間・交通費・労力を削減でき、「続けやすい診療体験」を得られます。特に忙しいビジネスパーソンや地方在住者にとって、オンラインでの継続診療は非常に魅力的です。
競合との差別化
都市部ではすでにオンライン診療を導入する美容クリニックやAGA治療専門クリニックが増えています。
「通いやすさ」や「柔軟な対応力」は患者がクリニックを選ぶ大きな基準となり、後発であってもブランド力向上につながります。
導入しやすい診療領域
オンライン診療と相性の良い領域は以下の通りです。
- 美容皮膚科(スキンケア相談、施術後の経過観察)
- AGA治療(定期処方・副作用チェック)
- ED治療(服薬相談・継続処方)
- 矯正歯科(事前カウンセリング・進捗確認)
- ピル処方(定期処方、服薬相談)
2. オンライン診療を始める前に確認すべきこと

法規制・診療ガイドライン
自費診療であっても、医師法・個人情報保護法などの法令遵守は必須です。オンライン診療の指針(厚生労働省のガイドライン)や、自治体ごとのルールを確認してから動き出しましょう。
対象診療メニューの選定
オンライン診療と相性が良いのは、診断の変動が少なく、継続処方や経過観察が中心の診療です。逆に、初診で精密検査が必要な治療や、緊急性の高い症状の診断には不向きです。まずはオンラインと相性が良く、院内リソース的にも負担が少ない診療から始めるのがおすすめです。
例:再診や経過観察、薬の処方など、診察内容が安定しているケース。
オンライン診療と相性の良いメニューに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
対面との併用
患者にとって安心なのは「初診は対面で、再診以降はオンライン」という流れです。この方式なら、医師側も正確な診断ができ、患者側も「見てもらったうえでオンライン診療に移行した」という安心感を得られます。
また、症状が悪化した際には対面に切り替えるルールを作っておくと、診療の質を維持できます。
スタッフのオペレーション準備
オンライン診療を導入すると、以下の業務が追加されます。
- 予約・リマインド通知
- 接続確認やトラブル対応
- 決済処理
- 処方薬の配送手配
これらは「誰が」「どのタイミングで」行うかを事前に決めないと、受付や看護師の業務が混乱します。オペレーションフローを作り、スタッフ全員が同じ流れで対応できる体制を整えることが重要です。予約管理、問診票の回収、診療前後の患者対応など、業務フローを事前に明確にしておきましょう。
3. オンライン診療導入の7ステップ

ステップ1:目的と対象患者を明確化する
オンライン診療を導入する際、最初に取り組むべきなのが「目的の明確化」です。
導入理由が曖昧なまま進めてしまうと、ツール選びやプロモーションの方向性がブレてしまい、成果につながりにくくなります。
まず「自分のクリニックは何のためにオンライン診療を取り入れるのか」を言語化することで、その後のツール選定・運用設計・プロモーション戦略まで一貫性を持って進めることができます。
例えばオンライン診療導入には、大きく分けて次のような目的があります。
- 新規患者の獲得
オンラインでの診療によってより広範囲から集客したいケース。 - 既存患者の継続率アップ
通院の負担を減らし、既存患者が継続して治療しやすくしたいケース。 - 院内業務の効率化
予約や決済を自動化して、スタッフの業務負担を軽減したいケース。
導入理由があいまいだと起こること
- 新規患者を獲得したいのに、院内告知しかせず広がらない
- 継続利用を狙っているのに、広告で初回体験ばかりを推してしまう
- 業務効率化が目的なのに、集客ばかりに注力してスタッフ研修がおろそかになる
つまり対象患者像が明確でなく、「誰に、何を伝えたいのか」が決まっていないと、広告コピー・集客チャネル・院内体制の設計がバラバラになり、結局期待した成果が得られません。
目的がツール選定に直結する理由
オンライン診療ツールは、機能や強みがそれぞれ異なります。目的を明確にすることで「どんな機能が必須で、どんな機能は不要か」が整理され、最適なツールを選定できるのです。
ステップ2:必要機能を整理する
オンライン診療ツールは多機能ですが、全部入りが最適とは限りません。
必要機能の例:
- 予約管理(自動受付、リマインド)
- 問診票(事前送信・回収)
- ビデオ通話診療(ブラウザ型 or アプリ型)
- 決済機能(クレジット、オンライン決済)
- カルテ連携(既存システムとの互換性)
導入目的から必要機能を考える
- 新規患者獲得が目的なら、アプリ不要で手軽に使えるツールや、LINE連携など患者が馴染みやすい仕組みが向いています。
- 継続率アップが目的なら、定期処方やリマインド通知が強いツールを選ぶと効果的です。
- 業務効率化が目的なら、既存の電子カルテや決済システムとスムーズに連携できるものを優先すべきです。
「必須」と「あると便利」を分類すると、コストも抑えられます。
ステップ3:オンライン診療ツールを選定する
ツール選びは導入成功のカギです。整理した必要機能をもとに最適なツールを選びましょう。
選定ポイント:
- 患者の使いやすさ(アプリ不要、LINE連携など)
- セキュリティ(通信暗号化、個人情報保護法対応)
- コスト(初期費用・月額・従量課金)
- サポート体制(導入時研修、運用後問い合わせ対応)
予約〜診療〜決済までの全体の患者体験が悪いと、患者の利用継続率が下がります。導入前に必ず細かく確認をするようにしましょう。
ステップ4:機器・インターネット環境を整える
最低限必要な環境:
- カメラ・マイク付きPCまたはタブレット
- 高速かつ安定したネット回線(有線接続推奨)
- 適切な照明と静かな診療スペース
オンライン診療を円滑に行うためには、安定したネット回線が不可欠です。特に、診療中の映像や音声の品質が患者満足度に直結するため、通信品質への投資は最優先で検討しましょう。
ステップ5:院内オペレーションを設計する
予約〜診療〜決済までの流れを事前に固めます。
例:
- 患者がWeb予約
- 自動送信メールで問診票リンクを案内
- 当日、受付が接続確認
- 医師が診療
- 決済完了後に処方・配送手配
このフローをマニュアル化し、スタッフ全員が同じ対応をできる状態にします。
ステップ6:スタッフ研修を行う
オンライン診療を導入する際は、スタッフ全員が一貫した対応ができるよう、ツール操作だけでなく、患者への説明スクリプトやトラブル時対応フローを共有し、定期的な研修を実施することが求められます。特に通信トラブルや接続方法がわからない患者へのフォロー体制は重要です。
ステップ7:患者への周知・プロモーション
オンライン診療を始めても、患者が知らなければ利用されません。どれだけ優れた仕組みを整えても、患者がその存在を知らなければ利用はゼロのままです。オンライン診療をスタートする際は、認知拡大と利用促進のプロモーションが欠かせません。
告知方法:
- 公式サイトに専用ページを作成
- SNS・メール配信で告知
- 院内ポスターやチラシを設置
- 初回限定キャンペーンで利用ハードルを下げる
目的に応じたプロモーション例
- 新規患者獲得が目的 → 「全国どこからでも受診可能」「初回カウンセリング無料」といったメッセージを打ち出し、Google広告やSNSを活用する
- 既存患者の継続率アップが目的 → 「再診はオンラインでOK」「忙しくても治療を続けられる」と伝え、院内ポスターやLINE配信で周知する
4. 導入時によくあるつまずきと解決策

オンライン診療は大きなメリットがある一方で、導入直後に「思っていたより運用が難しい」と感じるクリニックも少なくありません。ここでは、実際に院長やスタッフがつまずきやすいポイントと、その解決策を解説します。
ケース1:高齢患者やITに不慣れな患者が操作できない
オンライン診療は便利ですが、患者の年齢層やITリテラシーによっては「つなぎ方がわからない」「カメラが起動しない」といったトラブルが起きやすいです。
解決策
- ツールはできるだけ「アプリ不要」「LINEやブラウザで簡単に接続可能」なものを選ぶ
- 初回利用時にはスタッフが電話で接続サポートを行う
- 院内で配布する説明リーフレットを用意する
このように「患者に負担をかけない仕組み」を先に整えることで、利用ハードルを下げられます。
ケース2:無断キャンセルやドタキャンが増える
「対面よりも手軽」だからこそ、患者側が気軽に予約を入れてキャンセルするケースが増えることがあります。これは収益や診療効率を圧迫する大きな要因です。
解決策
- 事前決済を導入し、支払い完了後に予約確定する仕組みにする
- 自動リマインド通知を診療前日に送る
- 無断キャンセルが続く患者には「次回以降は対面のみ」といったルールを明示する
キャンセルを完全になくすことは難しいですが、仕組みでリスクを最小化することが可能です。
ケース3:スタッフが業務に慣れず混乱する
オンライン診療は従来の対面診療とは異なるフローが多く、特に導入初期は「誰がどこまで対応するのか」が曖昧になりがちです。その結果、二重対応や確認漏れが発生してしまいます。
解決策
- 予約受付から診療、決済、処方までの流れをマニュアル化する
- 月に1回程度の院内研修を行い、実際のトラブルを共有・改善
- 患者からの問い合わせに備えて「よくある質問集(FAQ)」をスタッフ向けに用意
オペレーションの明確化と継続的な研修が、現場の混乱を防ぎます。
ケース4:患者にオンライン診療が浸透しない
導入しても、患者が存在自体を知らなければ利用されません。「せっかく準備したのに予約が入らない」というケースも珍しくありません。
解決策
- 公式サイトやSNSで積極的に告知する
- 院内ポスターや診察時にスタッフから直接案内する
- 初回利用に限り割引や特典を用意し、利用ハードルを下げる
特に自費診療は患者の選択肢が多いため、「手軽で便利」と感じてもらう最初のきっかけ作りが大切です。
このように、導入時のつまずきは「患者側の課題」「スタッフ側の課題」「集客面の課題」に大別されます。最初から課題を想定し、仕組みとルールで解決策を整えておけば、オンライン診療をスムーズに定着させられるでしょう。
5. まとめ

オンライン診療は、自費診療クリニックにとって集客・継続率・満足度を一度に高められる手段です。ただし成功には、事前の目的設定・ツール選び・運用体制の整備が欠かせません。
今から始めても遅くはありません。まずは無料相談やデモ体験で、実際の運用イメージをつかみ、明確な導入計画を立てましょう。
Medibotでオンライン診療をもっと手軽に

オンライン診療の導入を検討する際、ツール選びは成功の鍵です。
Medibotは、自費診療・自由診療クリニック向けに設計されたオンライン診療プラットフォームで、以下の特徴があります。
簡単操作で患者もスムーズ
アプリのダウンロードは不要。患者はLINEやWebブラウザからすぐにアクセスでき、手軽に診療を受けられます。
高いセキュリティで安心
通信はすべて暗号化され、個人情報保護法に基づいた安全な環境を提供します。クリニック側も安心して導入可能です。
柔軟な料金体系とサポート
初期費用や月額費用、従量課金などクリニックの運営スタイルに合わせて選べます。導入時の研修や運用後のサポートも充実しています。
運用負担を軽減
予約管理、問診票の記入、決済までLINE上で完結。医師・スタッフの業務負担を減らし、患者対応に集中できます。
自費のオンライン診療ならMedibotにお任せください!

私達が提供しているMedibotは、LINE上で予約から決済まで完結できる、自費診療クリニックのためのオンライン診療ツールです。
予約・問診・オンライン診療・決済までLINE上で完結するので、アプリダウンロードは不要。患者様の満足度も、集患の効率も最大化できます。
また、マーケティング(集客)機能も充実しており、患者様のニーズに合わせてパーソナライズされた配信を自動で送ることが可能です。
新規予約の増加に加え、離脱防止や再来院促進までを一気通貫でサポートいたします。
導入・集患に関するご相談や資料請求はすべて無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください!
お気軽に
お問い合わせください
導入・集患に関する
ご相談や資料請求は全て無料です。
\ まずはお悩みをご相談ください /
無料で相談する\ Medibotの機能・活用事例がまるわかり /
資料をダウンロードする