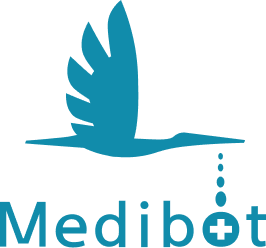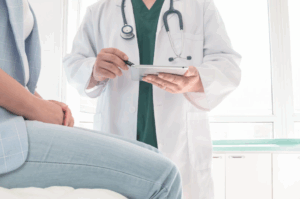オンライン診療の不安を解決!デメリット対策で導入を成功させるために

近年、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、医療現場におけるオンライン診療の導入が急速に進みました。感染症対策だけでなく、患者様の利便性向上や医療アクセスの改善に貢献するとして、その価値は広く認識されています。都市部だけでなく、医療過疎地域においても重要な役割を果たす可能性を秘めています。
しかし、新しい技術やシステムを導入する際には、必ずと言っていいほど疑問や不安がつきものです。特に、患者様の命や健康を預かる医療の現場では、その懸念はより一層強くなることでしょう。「対面診療と同じ質の医療を提供できるのか?」「セキュリティは大丈夫なのか?」「導入後の運用は複雑ではないか?」といった声が聞かれるのも無理はありません。
本記事では、オンライン診療を導入する上で多くの医療機関が懸念する主なデメリットに焦点を当て、それぞれの具体的な対策方法を詳しく解説します。デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、オンライン診療を単なる一時的な対応ではなく、クリニック経営の安定と、患者様へのより良い医療提供のための強力なツールとして活用できるようになるでしょう。
1. オンライン診療の主なデメリット

オンライン診療が持つ多くのメリットがある一方で、導入を検討する際に留意すべきデメリットもいくつか存在します。これらを事前に把握し対策を講じることが、スムーズな導入と効果的な運用には不可欠です。
1.1. 診察の質の低下の懸念

オンライン診療の最も大きな懸念の一つは、診察の質が対面診療に比べて低下する可能性です。
- 触診や視診の限界
患者様の患部に直接触れる触診や、詳細な皮膚の状態、目の動きなどを間近で観察する視診は、現在の技術ではオンラインで完全に再現することが困難です。これにより、診断の精度に影響を及ぼす可能性があります。例えば、腹部の張りやリンパ節の腫れ、皮膚の発疹の微妙な変化などを正確に把握することが難しい場合があります。 - 患者の表情や雰囲気の把握の難しさ
画面越しでは、患者様の細かな表情の変化や、言葉に表れない倦怠感、精神的な状態を察知しにくいことがあります。対面診療では自然と得られる情報が少なくなるため、患者様の全体像を把握するのが難しくなるケースも考えられます。 - 緊急時の対応の遅れ
診察中に患者様の容態が急変した場合、オンラインでは即座に適切な処置を施すことができません。救急対応が必要な状況で、医療機関への搬送や連携に時間を要するリスクも考慮する必要があります。
1.2. セキュリティとプライバシーのリスク

医療情報は非常に機密性が高く、セキュリティとプライバシーの保護はオンライン診療において最重要課題の一つです。
- 患者データの漏洩リスク
オンライン診療システムを介して送受信される患者様の個人情報や病歴、診察内容などのデータは、サイバー攻撃や不正アクセス、システム側の不備によって漏洩するリスクがゼロではありません。一度情報が漏洩すれば、患者様だけでなくクリニックの信頼性にも甚大な影響を与えます。 - 通信環境によるセキュリティの脆弱性
患者様や医療機関のインターネット環境が脆弱な場合、通信経路が傍受されたり、ウイルス感染のリスクが高まったりする可能性があります。公衆Wi-Fiなど、セキュリティレベルの低い環境での利用は特に注意が必要です。 - なりすましや不正アクセスの可能性
患者様本人以外の人物がオンライン診療を受ける「なりすまし」のリスクや、システムへの不正アクセスによって診察予約が乗っ取られるなどの事態も想定されます。これらは、適切な本人確認の仕組みがなければ防ぎきれません。
1.3. 患者層の限定と利用促進の課題

オンライン診療は誰もがすぐに利用できるわけではなく、利用できる患者層が限定されることや、利用促進に課題があることもデメリットとして挙げられます。
- ITリテラシーの低い高齢者層の利用が難しい
スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな高齢者層にとって、オンライン診療のアプリのインストールやアカウント登録、ビデオ通話の操作などはハードルが高い場合があります。結果として、必要とする層に医療が届きにくくなる可能性があります。 - オンライン診療への抵抗感や不慣れ
「オンラインではきちんと診てもらえない」「操作が難しそう」といった先入観や、新しい診療形態への抵抗感を持つ患者様も少なくありません。特に初めて利用する患者様にとっては、利用方法が分からず途中で断念してしまうケースも考えられます。 - 対面診療を希望する患者への対応
病状によっては、やはり直接医師に診てもらいたい、相談したいと考える患者様もいます。オンライン診療を導入しても、対面診療を希望する患者様のニーズにどのように応えるか、バランスの取れた体制づくりが求められます。
1.4. 導入・運用のコストと手間

オンライン診療の導入には、初期投資や運用に伴うコストと手間が発生します。
- 初期導入費用(システム、機材など)
オンライン診療システムそのものの利用料に加え、安定した通信を行うための高性能なパソコン、ウェブカメラ、マイク、セキュリティソフトなどの機材購入費用がかかります。クリニックの規模や既存設備によって、この初期投資額は変動します。 - スタッフの教育・研修コスト
新しいシステムを導入するにあたり、医師だけでなく、受付スタッフや看護師など、オンライン診療に関わる全てのスタッフがシステムの使い方や新しい業務フローを習得するための教育・研修が必要になります。これには時間と人件費がかかります。 - オンライン診療特有の事務作業の増加
予約の管理、患者様への事前連絡、処方箋や診断書の送付、オンライン決済の処理など、対面診療にはない事務作業が発生します。これらを効率的にこなすための業務フローの構築も必要です。
1.5. 法規制・ガイドラインの頻繁な変更

オンライン診療は比較的新しい医療形態であるため、関連する法規制やガイドラインが頻繁に更新される傾向にあります。
- 国の政策や指針による変更への対応
厚生労働省が発出するオンライン診療に関するガイドラインや料金体系(保険診療における診療報酬、自費診療におけるサービス料金)に関する改定は、定期的に行われます。これらの変更に迅速に対応し、適切な診療体制を維持していく必要があります。変更を見落とすと、法令違反につながる可能性もあります。 - 地方自治体独自のルールへの適応
国のガイドラインに加え、特定の地方自治体が独自のオンライン診療に関するルールを設ける場合もあります。クリニックが所在する地域のルールを正確に把握し、それに従う必要があります。これにより、クリニック側の負担が増えることも考えられます。
2. 各デメリットへの具体的な対策

前述したデメリットは、適切な対策を講じることで十分に克服可能です。ここでは、それぞれのデメリットに対する具体的な対策方法を詳しく解説します。
2.1. 診察の質の低下の懸念への対策

診察の質を維持・向上させるためには、情報の補完と環境整備が重要です。
- 事前の情報共有の徹底
オンライン診療の前に、詳細な問診票の記入を患者様に依頼し、病状や既往歴、服用中の薬剤などを正確に把握します。必要に応じて、事前に患者から検査結果や患部の写真などを送ってもらう仕組みを導入することも有効です。これにより、医師は限られた情報の中で最適な判断を下すための材料を増やすことができます。 - 高画質・高音質の通信環境の確保
安定したインターネット回線(光回線など)を導入し、高性能なウェブカメラやノイズキャンセリング機能付きのマイクを使用することで、診察時の映像と音声の品質を最大限に高めます。これにより、患者様の細かな表情や声のトーン、患部の状態などをより正確に把握できるようになります。 - 緊急時のプロトコルの確立
診察中に患者様の容態が急変した場合に備え、事前に緊急時の対応プロトコルを策定しておきましょう。例えば、近隣の連携医療機関との協力体制を構築し、緊急搬送が必要な場合に迅速に手配できるような手順を明確にします。患者様にも、事前に緊急時の連絡先や対応方法を伝えておくことが重要です。 - 対面診療との併用(ハイブリッド診療)
すべての患者様をオンライン診療に移行するのではなく、病状に応じて対面診療とオンライン診療を組み合わせる「ハイブリッド診療」を導入しましょう。例えば、初診は対面で行い、症状が安定している再診はオンラインで行う、あるいは、オンラインで診察し、必要に応じて対面診療への切り替えを促すといった柔軟な運用が可能です。これにより、オンライン診療の利便性を享受しつつ、診察の質を確保できます。 - オンライン診療に適したメニューの選定
そもそもオンライン診療に向いている症状や疾患、再診患者など、オンラインでも十分な質の診療を提供できるメニューから導入を始めることが重要です。例えば、慢性疾患の定期的な処方や生活習慣病の指導、メンタルヘルス相談、服薬がメインの自費診療など、視診や触診の必要性が低いケースや、患者さんの状態が安定しているケースから取り入れることで、医療の質を維持しやすくなります。
2.2. セキュリティとプライバシーのリスクへの対策

患者様の大切な情報を守るためには、システム選定と運用体制の強化が不可欠です。
- セキュアなオンライン診療システムの選定
システムを選ぶ際には、医療情報に関するセキュリティ基準(例:ISO27001などの国際標準認証)を満たしているかを必ず確認しましょう。データの暗号化、二段階認証、アクセスログの監視機能など、強固なセキュリティ対策が施されているシステムを選ぶことが最も重要です。 - 患者様への情報提供と同意の取得
オンライン診療を行う前に、プライバシーポリシーを明確に提示し、患者様のデータがどのように扱われるのか、どのようなセキュリティ対策が講じられているのかを丁寧に説明し、同意を得るようにしましょう。これにより患者様は安心して診療を受けることができます。 - スタッフへのセキュリティ教育
医師だけでなく、全てのスタッフに対して、情報セキュリティに関する定期的な教育・研修を実施しましょう。パスワードの適切な管理方法、不審なメールやサイトへの注意喚起、患者情報の取り扱いに関するルールなどを徹底することで、内部からの情報漏洩リスクを低減できます。 - 定期的なセキュリティチェックとアップデート
導入後も、システム提供者からのセキュリティアップデートは迅速に適用し、定期的にクリニック内のネットワーク環境や使用機器のセキュリティチェックを行いましょう。これにより、新たな脅威に対応し、常に最新のセキュリティレベルを維持することができます。
2.3. 患者層の限定と利用促進の課題への対策

より多くの患者様にオンライン診療を利用してもらうためには、利用へのハードルを下げ、メリットを積極的に伝えることが大切です。
- デジタルデバイド対策
ITリテラシーの低い患者様、特に高齢者層に対しては、操作マニュアルを分かりやすく作成したり、電話での導入サポート窓口を設置したりするなど、きめ細やかなサポート体制を整えましょう。初回利用時には、スタッフが丁寧に操作方法を説明する時間を作ることも有効です。 - オンライン診療のメリットの積極的な広報
クリニックのホームページや待合室、SNSなどを活用して、オンライン診療のメリット(待ち時間の短縮、移動負担の軽減、感染リスクの回避、自宅や職場から手軽に受診できる点など)を具体的にアピールしましょう。患者様が「これなら使ってみたい」と思えるような情報発信が重要です。 - 患者様への丁寧な説明と安心感の提供
初めてオンライン診療を利用する患者様には、事前に診察の流れや注意事項を丁寧に説明し、疑問や不安を解消できるように努めましょう。Q&Aページを充実させたり、よくある質問に答える動画を作成したりすることも効果的です。医師やスタッフが患者様の不安に寄り添う姿勢を見せることで、安心感を提供できます。 - 予約システムの簡素化
オンライン診療の予約プロセスを可能な限りシンプルにし、患者様が迷わず予約できるように工夫しましょう。クリック数を減らし、直感的に操作できるデザインの予約システムを選ぶことが、利用促進につながります。
2.4. 導入・運用のコストと手間への対策

コストと手間を最小限に抑え、効率的な運用を目指しましょう。
- 補助金・助成金の活用
国や地方自治体では、オンライン診療システムの導入を支援するための補助金や助成金制度が設けられている場合があります。これらの情報を積極的に収集し、活用することで、初期導入費用や運用コストの負担を軽減できます。情報収集は、自治体のウェブサイトなどで確認できます。 - シンプルなシステムとサポート体制の選定
操作が直感的で分かりやすいオンライン診療システムを選びましょう。また、導入後のトラブルや疑問点に迅速に対応してくれる充実したサポート体制があるかどうかも重要な選定基準です。サポートの質は、導入後のスムーズな運用に大きく影響します。 - スタッフへの業務フローの明確化と効率化
オンライン診療導入に伴う新しい業務フローを具体的に定め、各スタッフの役割と責任を明確にしましょう。予約受付から、診察前の準備、診察中のサポート、診察後の会計・処方箋発行までの一連の流れを最適化し、無駄をなくすことで、スタッフの負担を軽減し、効率的な運用が可能になります。
2.5. 法規制・ガイドラインの頻繁な変更への対策

常に最新の情報を把握し、柔軟に対応できる体制を構築しましょう。
- 最新情報の定期的な収集
厚生労働省のウェブサイトや、日本医師会などの医療関係団体からの情報提供に常にアンテナを張り、オンライン診療に関する最新の法規制やガイドライン、料金体系に関する情報を定期的にチェックしましょう。信頼できる情報源から正確な情報を得ることが重要です。 - 専門家との連携
医療法務に詳しい弁護士や医療コンサルタントと連携し、法規制の解釈や対応について相談できる体制を整えることも有効です。特に複雑なケースや、自院の特殊な状況に合わせた判断が必要な場合に、専門家の助言は大きな助けとなります。 - 柔軟なシステム対応
導入するオンライン診療システムが、法改正やガイドラインの変更に迅速に対応し、アップデートされるかどうかを確認しましょう。システム自体が法規制の変更に追従できる柔軟性を持っていることが、将来的なリスクを回避する上で非常に重要です。
3. Medibotが提供するソリューション

「Medibot」は、クリニックの皆様がオンライン診療を安心して、そして効果的に導入・運用できるよう、これらのデメリットに対する具体的なソリューションを提供しています。
Medibotは、データの暗号化やアクセス制限、アクティビティモニタリングなどを通して安全性を確保し、患者様の大切な医療情報を厳重に保護します。国際的なセキュリティ基準に準拠した設計で、データ漏洩のリスクを最小限に抑えます。また、医師と患者様双方にとって直感的で分かりやすいUI/UXを追求しており、ITリテラシーに自信がない方でもスムーズに操作できるよう設計されています。複雑な操作に悩むことなく、オンライン診療本来のメリットを最大限に享受できます。
導入前から運用後まで、充実したサポート体制もMedibotの強みです。専任のサポートチームが、システムの導入設定から、スタッフへの操作説明、日々の運用における疑問やトラブル対応まで、手厚く支援いたします。
Medibotは、単なるオンライン診療ツールではなく、クリニックのオンライン診療を成功に導くための強力なパートナーです。
4. まとめ

オンライン診療は、現代の医療において非常に有効な手段であり、患者様の利便性向上や医療アクセスの改善、そしてクリニック経営の効率化に大きく貢献する可能性を秘めています。たしかに、診察の質、セキュリティ、患者層の限定、コスト、そして法規制の変化といったデメリットは存在します。しかし、本記事でご紹介したように、これらのデメリットは適切な知識と具体的な対策を講じることで、十分に克服することが可能です。
重要なのは、これらの課題から目を背けるのではなく、事前にしっかりと理解し適切な準備と信頼できるオンライン診療ツールを選定することです。充実したサポートと強固なセキュリティを備えたシステムを選ぶことで、オンライン診療への一歩を踏み出す不安を解消し、クリニックの新たな可能性を広げることができるでしょう。
オンライン診療を導入することは、クリニック経営を新たな次元へと引き上げ、より多くの患者さんに質の高い医療を提供するための大きなチャンスです。
自費のオンライン診療ならMedibotにお任せください!

私達が提供しているMedibotは、LINE上で予約から決済まで完結できる、自費診療クリニックのためのオンライン診療ツールです。
予約・問診・オンライン診療・決済までLINE上で完結するので、アプリダウンロードは不要。患者様の満足度も、集患の効率も最大化できます。
また、マーケティング(集客)機能も充実しており、患者様のニーズに合わせてパーソナライズされた配信を自動で送ることが可能です。
新規予約の増加に加え、離脱防止や再来院促進までを一気通貫でサポートいたします。
導入・集患に関するご相談や資料請求はすべて無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください!
お気軽に
お問い合わせください
導入・集患に関する
ご相談や資料請求は全て無料です。
\ まずはお悩みをご相談ください /
無料で相談する\ Medibotの機能・活用事例がまるわかり /
資料をダウンロードする