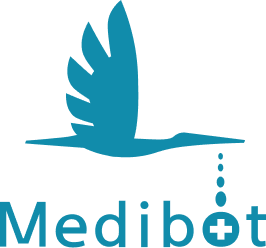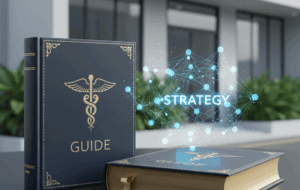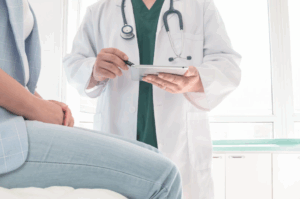【開業医向け】オンライン診療ツール導入のスケジュール|最短で始める5ステップ

近年、医療の現場ではデジタル化が急速に進み、オンライン診療はもはや特別なものではなくなりました。患者さんの利便性を高め、通院の負担を軽減するだけでなく、新しい患者層を獲得するチャンスでもあります。
しかし、「導入したいけれど、何から手をつければいいのか分からない」「どれくらいの期間とコストがかかるの?」といった疑問を抱えているクリニックも少なくありません。
この記事では、オンライン診療ツールの導入を検討している院長や事務長向けに、具体的な導入スケジュールを5つのステップに分けて徹底的に解説します。この記事を読めば、効率的かつ確実にオンライン診療をスタートさせるためのロードマップが明確になるでしょう。
導入にかかる期間の全体像:平均的なスケジュール

オンライン診療ツールの導入には、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要です。もちろん、クリニックの規模や選ぶシステムによって期間は前後しますが、以下のステップを踏むことで、スムーズに運用開始までたどり着くことができます。
| ステップ | 期間の目安 |
| Step 1:導入検討・情報収集 | 1〜2週間 |
| Step 2:システム契約・機材準備 | 1週間〜1ヶ月 |
| Step 3:法的手続き・院内体制の整備 | 1〜2週間 |
| Step 4:患者さんへの告知・運用準備 | 1〜2週間 |
| Step 5:運用開始・効果検証 | 継続的 |
それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。
Step 1:導入検討・情報収集(目安:1〜2週間)

まず、オンライン診療を導入する目的を明確にすることから始めます。「なぜオンライン診療を導入したいのか?」を考えることで、最適なツール選びにつながります。
- 再診患者のフォローアップを効率化したい
- 遠方に住む患者さんにも診療を提供したい
- 自由診療(美容、ダイエットなど)の新規患者を獲得したい
目的が定まったら、ツールの比較検討に入ります。数多くのオンライン診療ツールが存在するため、以下のポイントに注目して絞り込みましょう。
1. 必要な「機能」は何か?
- 予約機能:Webサイトやアプリからの予約受付。
- 決済機能:オンラインでのクレジットカード決済。
- 電子カルテ連携:既存の電子カルテと連携できるか。
- 問診票機能:オンラインで事前に問診票を記入してもらう。
- ビデオ通話機能:安定した通信環境でのビデオ通話。
- チャット機能:診療後の簡単な相談や連絡に利用。
2. 「サポート体制」は充実しているか?
導入時の設定支援や、運用中のトラブル対応など、ベンダーのサポート体制は非常に重要です。特に初めて導入する場合は、手厚いサポートがあるツールを選ぶと安心です。
3. 「コスト」はどのくらいか?
初期費用、月額費用、そして診療件数に応じた従量課金制など、コスト構造はツールによって異なります。長期的な視点で、費用対効果を試算しましょう。
多くのベンダーが無料トライアルやデモを提供しています。実際に操作感を試すことで、自院の運用に合うかどうかを判断できます。
Step 2:システム契約・機材準備(目安:1週間〜1ヶ月)

比較検討を終え、導入するツールが決まったら、いよいよ契約です。
1. 契約手続き
利用規約や契約内容を十分に確認し、契約を締結します。この段階で、導入後のサポート内容や料金体系について最終確認しておきましょう。
2. 必要な機材の準備
オンライン診療に必要な機材は比較的シンプルです。
- PC、タブレット、スマートフォン:診療に利用する端末。複数台用意しておくと安心です。
- ウェブカメラ、マイク、スピーカー:高画質・高音質なものを用意することで、患者さんとのコミュニケーションがスムーズになります。
- 安定したインターネット回線:オンライン診療の品質は通信環境に大きく左右されます。光回線など、安定した環境を整備しましょう。
3. アカウント設定・システム環境構築
ベンダーのサポートを受けながら、クリニック側のアカウント作成、スタッフ用アカウントの発行、電子カルテ連携の設定などを行います。この時点で、運用に必要な基本的な設定をすべて完了させておきましょう。
Step 3:法的手続き・院内体制の整備(目安:1〜2週間)
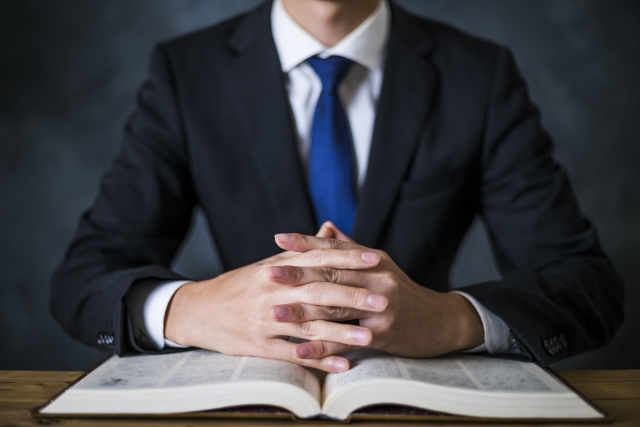
オンライン診療の運用を始めるには、法的な手続きと院内の体制整備が不可欠です。
1. 主なルールと注意点
オンライン診療の運用は、前提として厚生労働省が定めた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って行う必要があります。その他詳細は以下の厚生労働省の資料等を参考にしてください。
【参考資料】
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(PDF/578 KB)
厚生労働省「オンライン診療の利用手順の手引書」
厚生労働省「オンライン診療研修(eラーニング)」
関東信越厚生局「施設基準の届出等」
2. 院内ルール・マニュアルの作成
オンライン診療を円滑に進めるためには、スタッフ全員が共通の認識を持つことが重要です。自由診療の特性に合わせた以下の内容を含むマニュアルを作成しましょう。
- 診療の対象患者・疾患の基準:自由診療でオンライン診療を行う場合、安全性を確保するため、初診の対面診療の有無や、対象となる疾患や症状の基準を明確にします。
- 予約から決済、配送までのフロー:オンラインでの予約、決済、そして処方薬や商品の配送まで、各ステップで誰が何をすべきかを明確にします。
- トラブル発生時の対応手順:通信不良や決済トラブルなど、想定されるトラブルへの対処法を定めます。
- 患者さんへの説明方法:オンライン診療と対面診療の違い、料金体系、利用方法などを分かりやすく説明するスクリプトを用意します。
3. スタッフへの研修
作成したマニュアルを基に、スタッフ全員がツールの操作方法を習得できるよう研修を行います。実際に模擬診療を実施し、運用フローをシミュレーションすることで、本番での戸惑いを減らし、質の高いサービス提供につなげることができます。
Step 4:患者さんへの告知・運用準備(目安:1〜2週間)
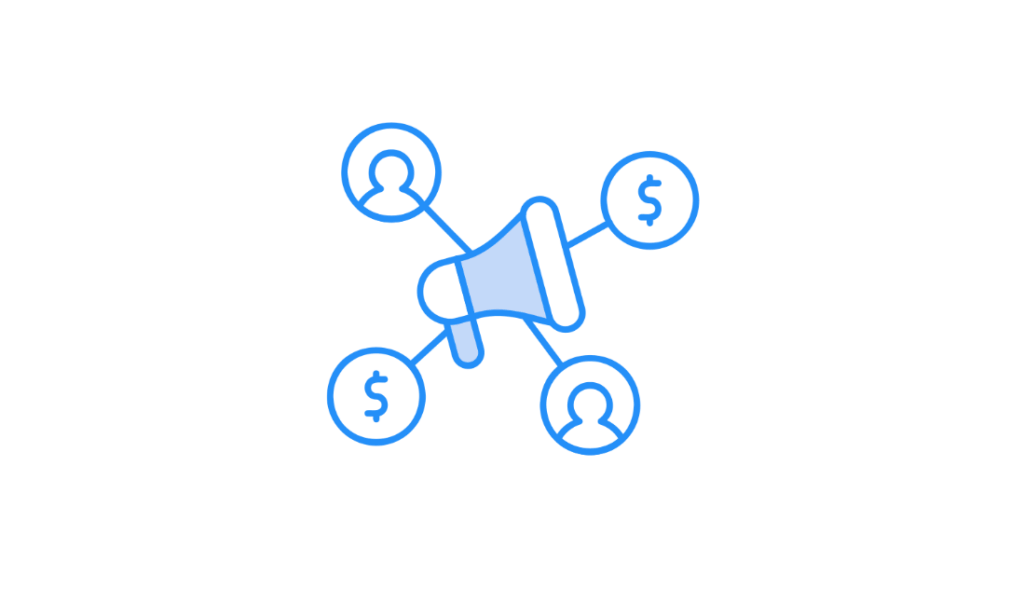
システムの準備が整っても、患者さんに知ってもらわなければ始まりません。効果的にオンライン診療の存在を周知しましょう。
1. 告知方法
- 院内ポスター・チラシ:待合室や診察室に設置し、対面診療で来院した患者さんに直接アピールします。
- クリニックのWebサイト・SNS:トップページにバナーを設置したり、SNSで導入のメリットを定期的に発信したりします。
- 受付での声かけ:「次回からオンライン診療もご利用いただけます」といった声かけで、関心を持ってもらいましょう。
2. 患者さん向けマニュアルの作成
オンライン診療に慣れていない患者さんも多いでしょう。ツールダウンロード方法、予約方法、診療当日の流れなどをまとめた分かりやすいマニュアルを作成し、Webサイトに掲載したり、受付で配布したりすると親切です。
Step 5:運用開始・効果検証(継続的)

いよいよオンライン診療の運用開始です。最初は無理せず、再診患者さんや比較的簡単な疾患に絞って始めることをお勧めします。
運用を開始したら、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を継続的に回し、改善を重ねていくことが成功の鍵です。
- P(計画):月間のオンライン診療件数など、具体的な目標を設定します。
- D(実行):実際にオンライン診療を実施します。
- C(評価):目標の達成度、患者さんからのフィードバック、スタッフの意見などを収集し、課題を洗い出します。
- A(改善):洗い出された課題を解決するために、運用ルールやマニュアルを見直します。
患者さんからの「予約が取りにくい」「ツールの操作が難しい」といった声は、サービスを改善するための貴重なヒントです。これらの声を活かし、より利便性の高いオンライン診療へと成長させていきましょう。
まとめ
オンライン診療の導入は、複雑に感じるかもしれませんが、この記事で紹介した5つのステップに沿って進めれば、決して難しいものではありません。
重要なのは、「何のためにオンライン診療を導入するのか」という目的を明確にし、自院に合ったツールを慎重に選ぶことです。そして、導入後も継続的に改善を重ねていくことで、オンライン診療はクリニックの新しい収益の柱となり、患者さんとの関係をさらに深めることができます。
オンライン診療にかかるコストや費用回収については以下の記事を参考にしてください!
自費のオンライン診療ならMedibotにお任せください!

私達が提供しているMedibotは、LINE上で予約から決済まで完結できる、自費診療クリニックのためのオンライン診療ツールです。
予約・問診・オンライン診療・決済までLINE上で完結するので、アプリダウンロードは不要。患者様の満足度も、集患の効率も最大化できます。
また、マーケティング(集客)機能も充実しており、患者様のニーズに合わせてパーソナライズされた配信を自動で送ることが可能です。
新規予約の増加に加え、離脱防止や再来院促進までを一気通貫でサポートいたします。
導入・集患に関するご相談や資料請求はすべて無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください!
お気軽に
お問い合わせください
導入・集患に関する
ご相談や資料請求は全て無料です。
\ まずはお悩みをご相談ください /
無料で相談する\ Medibotの機能・活用事例がまるわかり /
資料をダウンロードする